巷で溢れた2025年7月5日と8月15日の大艱難は訪れることはありませんでした。誠に同慶の極みですが、御承知の通り、未だ、我国の患難である確信犯的売国・亡国・反日政府I墓政府は辞任しようとしません。それどころか、この度の全国戦没者追悼式では、匍匐前進ながらも安倍元総理が進めてきた戦後レジームからの脱却に向けた思いを否定し、1994年に村山富市氏が使いその後の2012年に野田佳彦氏が使った「深い反省」という言葉に近似したもういい加減にして欲しい「反省」という語句を使用しました。やはりリベラルな戦後レジーム保守の敗戦利得者だということを体現していますよね。
そのような中でも、若手の国会議員の方々が、8月15日の敗戦記念日に靖国神社を訪れ、国難に散華された戦没者に対し哀悼の誠を捧げられ、日本が二度と戦争の惨禍に巻き込まれないように祈念してくださったことは大変有難いことでした。やはり、最近の若い人は素晴らしいですね。
愁伯は、九州の田舎に所在しているため、靖国神社に参拝することはなかなか叶いませんが、敗戦記念日には県の護国神社を訪れ、戦没者の方々に感謝の気持ちを伝え我国體の弥栄と諸国家の共存共栄を祈ってきました。加えて、今年は、より地元の英霊のことに焦点を当て見ようと、お盆の期間を使って、夫婦夫々の御先祖様のお墓参りを済ませた後に、孫達と一緒にその場所の数か所を訪れることにしました。
その大きな契機となったのは、上島嘉朗氏のyoutube「遠くの声をさがして」の一つに、北九州市若松区の埋め立て地にある軍艦堤防や同区の高塔山の中腹にある戦没者慰霊の塔が紹介されていたことでした(その中で、火野葦平氏の父玉井金五郎を題材にした高倉健氏主演の映画『花と龍』を教えていただいたことも大変嬉しかったのですが、)。
若松区は、それほど遠くではないため、まず、13日にその場所を訪れ、大和随伴艦の「涼月」及び「冬月」の二艦と第一次大戦で地中海へ派遣された「柳」の計三艦が大東亜戦争後、若松区の堤防の一環として係留され沈められたことを知りました。その内、「柳」の面影はセメント堤防の中に見ることができました(他の二艦は埋め立て地の中に埋まってしまっているとのことでした。)が、還暦を過ぎてから久しいというのに、近くの遺構であるにも関わらず初めての訪問でしたので、大変恥ずかしく、感謝とお詫びの気持ちを捧げてきました。
そこで、まだ他にもきっとあるだろうと思い、「戦争遺跡マップ」等を調べてみると、同じく北九州市八幡西区に「体当たり勇士の碑」というのがひっそりと佇んでいることに目が留まりましたので、14日にここを訪れました。この記念碑は、1944年8月20日北九州に来襲したアメリカのB29編隊80機編隊に対して小月飛行場から迎撃に向かった野辺重夫軍曹と高木伝蔵兵長の2人乗り戦闘機1機が体当たり攻撃をおこない爆撃機2機を同時に墜落させ散華されたことを顕彰するために、地元住民により昭和53年に建立されたものでした。ここは、折尾南2号公園の一角の森の中の目につかない場所にありましたが、それでも、記念碑は綺麗に手入れされ、その前には御花やお酒等の供物が捧げられており、何か特別の日には国旗が掲揚されるであろうところの掲揚塔が戦後70周年記念として地元の保存会の有志により築かれていました。孫達と一緒に哀悼の誠を捧げてきましたが、この戦後70年という節目と綺麗に手入れされた記念碑に、地元の最近の若い人たちの御尽力の跡が伺われ、温かい感謝の気持ちでいっぱいになりました。
その後で、小倉北区の足立山山麓にある平和公園の中の忠霊塔に参拝してきました。 ここは、1942年千堂陸軍墓地(現南小倉小学校)が手狭になったため当地を陸軍墓地として整備した際に建立されたものだということですが、その立派さは、宮崎市の平和台公園にある「八紘一宇の塔」に似た佇まいを感じました。ここにも、花が手向けられてあり、哀悼の誠を捧げるとともに、最近の若い方々の真摯な気持ちに有難くなる一方、やはり初めての訪問であることに恥じ入るばかりでした。
そして、15日は、宗像大社の北側に隣接してひっそりと鎮座される宗像護国神社にお参りしてきました。毎年は、福岡県の護国神社にお参りしていましたので、それなりに多くの方々がお参りに来られる様子を拝見しておりましたが、今年は近くの小さな護国神社でしたので、参拝される人は僅かでした。愁伯より年配の団塊世代の方々にお目にかかることは皆無でしたが、それでも、愁伯よりはずっと若い方々が三々五々に訪れており、やはり「日本は捨てたものじゃない。これからだ。最近の若い人は素晴らしい。」と気付かされました。
「最近の人は素晴らしい。」と思わされることは、このようなところにも沢山あるのですね。大人は、この素晴らしい最近の若い人たちに、素晴らしい日本を繋いでいく責任があることを忘れてはいけませんよね。

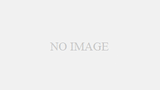
コメント